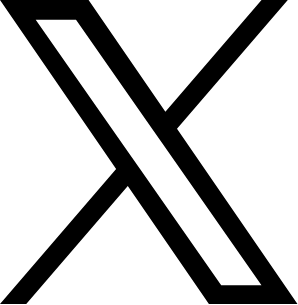Magazine

Interview
山崎隼セクステットのメンバーがSNSで寄せられた質問に回答!音楽家として決心を語る
ドラム 山崎隼、ピアノ 草田一駿、トランペット 鈴木雄太郎、ベース 廣橋契、アルトサックス 鈴木真明地、テナーサックス 山中龍之介
- 2025/04/25
- 2025/04/25
Profile
-

山崎隼(やまざき はやと)
山崎隼(やまざき はやと)
2001年愛知県生まれ。音楽好きの両親の影響で3歳からドラムを叩き始める。高校生ソロプレイヤーズコンテストを始め、数々の賞を受賞。Seiko Summer Jazz Camp 2022ではスピリット・オブ・ジャズ賞を受賞。現在はジャンルを問わずドラマー/パーカッショ二ストとして活動。YAMAHAエンドーサー。
-

草田一駿(そうた かずとし)
草田一駿(そうた かずとし)
1999年広島県生まれ。5歳よりピアノを始め、13歳よりジャズやロック等に開眼し、同時に作曲も始める。Seiko Summer Jazz Camp 2016にてBest Composition and Arrangement Award を受賞。著名アーティストとの共演やサポート、レコーディング、CM音楽制作など幅広く活動。
-

鈴木雄太郎(すずき ゆうたろう)
鈴木雄太郎(すずき ゆうたろう)
1995年新潟県生まれ。YAMANO BIG BAND JAZZ CONTESTにて2度の優勝を果たす。現在はコンボスタイルでの演奏に力を入れており、著名アーティストとの共演やサポート、レコーディング、映画主題歌への参加など幅広く活動。2016年のSeiko Summer Jazz Camp 第1期生。
-

廣橋契(ひろはし けい)
廣橋契(ひろはし けい)
1999年千葉県生まれ。大学でビッグバンド、モダンミュージックソサイエティに入部、コントラバスとジャズに出会う。現在は、都内を中心にライブやセッションなどの演奏活動を行っている。2022年のSeiko Summer Jazz Camp 第5期生。
-

鈴木真明地(すずき まあち)
鈴木真明地(すずき まあち)
2003年名古屋市生まれ。6歳からサクソフォンとタップダンスを始め、クラシックとジャズを学ぶ。高校生ソロプレイヤーズコンテストを始め、数々の賞を受賞。Seiko Summer Jazz Camp 2023ではスピリット・オブ・ジャズ賞を受賞。現在、国立音楽大学ジャズ専修4年。
-

山中龍之介(やまなか りゅうのすけ)
山中龍之介(やまなか りゅうのすけ)
2004年東京都生まれ。 中学生から高田馬場イントロに通い、セッション経験を積む。17歳からは、大江陽象氏率いる Asian Soul Boppers に参加し、ライブの出演を始める。現在は横浜国立大学3年生、モダンジャズ研究会に所属。
※SeikoSJC卒業生ではありません。
2025年4月6日にSeiko Summer Jazz Camp Graduates Live in Tokyo vol.41が東京・高田馬場にある<Café Cotton Club>で開催されました。会場に集まった大勢の観客を前に白熱の演奏を繰り広げたのは、Seiko Summer Jazz Camp 2022で優秀賞を受賞し、現在はプロのドラマーとして大活躍中の山崎隼さん率いるセクステット! 若さみなぎるプレーを2ステージ繰り広げた後は、ジャムセッションも行なわれ、見渡せば誰もが笑顔の花盛り。興奮冷めやらぬ空気をまとったメンバー全員に直撃インタビューを決行し、Seiko Summer Jazz Camp(以下、SeikoSJC)に関心のある方々からSNSを通じて寄せられた質問に本音で答えていただきました。
取材・文:菅野聖
撮影:樋口勇一郎
取材日:2025年4月6日
Q:楽器を始めたばかりの自分に、今、どんなアドバイスをしたいですか?
山崎隼(Dr):僕の父はトランペット、母はドラム、祖母は自宅でピアノ教室を開いていました。家には様々な楽器があり、それらを幼い頃から自由に触れたので、ドラムもいつの間にか叩いていたんです。その頃の僕に言いたいことは“感覚的に好きになったものをとことん突き詰めた方がいい”ということですね。周囲の言葉に惑わされず、自分を信じて進んで行くことが大切だと今、確信しています。それと“行きたいライブには無理をしてでも足を運ぼう”かな。名古屋在住だった僕は小学生の時、ものすごく行きたかったライブの会場が東京だったので諦めたことがあります。今にして思えば親に頼み込んででも連れて行ってもらえばよかった。だって、いつ、生演奏を見られなくなるかわかりませんからね。とにかく、やりたいことは絶対にやった方がいいです。

草田一駿(P):僕は5歳からクラシックピアノを習い始めました。当時、先生から言われた言葉を過剰にというか、拡張して受け止めていたようで、誰かの影響を受けることは良くないと思い込んでいたんです。弾き方は自分で見つけるべきだと思っていたので、ピアニストの演奏を聴いたり見たりすると模倣になってしまうと決めつけていました。もちろん、そんなことはありませんし、逆に、先人たちの演奏をもっと聴いておけばよかったと反省しています。特にジャズは様々なミュージシャンの演奏をきちんと聴くことが大前提。ジャンル問わず、全ての音楽は聴くことが始まりですから。
廣橋契(B):僕は大学のビッグバンドのサークルに入ってからジャズと出会いました。その時に初めてウッドベースに触れたので、最初は右も左も全くわからず、先輩から受け取ったレイ・ブラウン(B)の教則本を使って練習していました。その頃の自分にアドバイスをするとしたら“きちんと調整されている楽器を使おう”です。当時、使用していたベースはメンテナンスがされておらず、弾いていると手が痛くなり、原因は楽器に慣れていない自分のせいだと思っていたのですが、先輩のライブを聴きに行った時にベースを触らせてもらったら、すごく弾きやすかったんですよ。そこで初めて、調整されている楽器を知ったわけです。プレーヤーにとって楽器は本当に大切です。SeikoSJCに参加すれば、ベストな状態の楽器を知り尽くしている先生がいらっしゃるので、楽器を知るという意味でも良いチャンスだと思います。

鈴木真明地(As):小学1年生からサックスを吹き始めました。何もわからないままビッグバンドで演奏し、中学に入ってから本格的にジャズと向き合うようになったのですが、今、改めて感じているのは、楽器を始めた小学生時代からジャズに関心を持てばよかったということです。その頃、家では兄や姉の会話でジャズミュージシャンの名前が飛び交っていたのに、僕は彼らのことを深く知ろうとしなかったんですよ。YouTubeなども使える環境でしたから、もっと活用すればよかったと後悔しています。ジャズの名盤や時代背景、ミュージシャンの繋がりなどを知れば知るほどジャズは楽しくなりますし、自分自身も豊かになりますからね。
鈴木雄太郎(Tp):トランペットを始めたのは小学校5、6年生の頃。当時の僕に言いたいことは、自分にとってのアイドル的なミュージシャンの演奏を聴くに留まらず、サイドメンにも目を向けよう、ということです。僕の場合、アイドルはチェット・ベイカー(Tp、Vo)で、後々、サイドメンを追っていったら多くの気づきがありました。それと、様々なミュージシャンのバラードを採譜するとコードチェンジの違いが明確にわかりますし、色彩観も養われるので、バラードを聴けと若かりし日の自分に言いたいです。
山中龍之介(Ts):小学校3年生からテナーサックスを習い始めましたが、本気で練習するようになったのは中学生ぐらいからでした。その頃の自分に言いたいことは“きちんと音源を聴こう”です。当時、僕はアドリブができるようになりたいという気持ちが先行し、ひとつでも多くのフレーズを覚えることに意識が向いていました。でも、いくらフレーズを覚えて吹けるようになったとしても、その時、何を思って、何を感じて吹いているのか、というようなことを大切にしていなければ、単なるものまね師になってしまいます。ですから、メロディを歌えるようになってからコピーした方がいいよ、と言いたいですね。それと、素晴らしいと言われている音源はジャズ以外も聴いてみる、極論をいえば、楽器を触る前にまずは聴け!かな。

Q:Seiko Summer Jazz Campの応募に向けて特別な練習はしましたか?
廣橋:募集要項をチェックしたのは好奇心からでした。その時は自分のレベルでオーディションに受かるはずはないと思っていましたからね。ただ、そこに書かれていることは練習の参考にはなりましたよ。それまでの僕はベーシストだから後ろで支えることに躍起になり、ソロをとることは優先順位として高くなかったんです。でも、“メロディを弾く”“ソロをとる”と記されていたので、そこからの1年間は集中的にそれらの練習をしました。結果的に2022年のオーディションに通りましたが、だからといってSeikoSJCの参加を目標に練習していたわけではありません。あくまで、自分の音楽的な過程としての練習を続けていましたし、それが大事だと今も思っています。
鈴木真亜地:僕は大学1年生の時に応募して落選したんです。それもそのはず、あの時はまだコードを覚えようとしていた時期で、実際には、楽譜に書いてあるコードを見ながら吹くことしかできませんでした。その後、懸命にコードを覚え、それによって曲がどこに向かっていくのかという先の見通しができるようになり、曲自体が脳に沁みついたんです。コード進行が身体に入り、いつでもスムーズに歌えるようになった曲で、翌年、オーディションに再チャレンジしたら合格しました。SeikoSJCに応募するためだけにコードを覚えたわけではありませんが、そういう時期に重なったのは良かったと思っています。

草田:僕は2016年に開催された第1回に参加しました。当時はジャズを知った気でいた井の中の蛙のような、広島在住の高校2年生で(笑)、同郷の大林武司(P)さんからSeikoSJCのことを教えていただき、挑戦したんです。その頃と今では少しエントリー方法が違っているようですが、僕はオリジナル曲でチャレンジし、受講中にメンバーが僕の曲を演奏してくれて、作曲賞を受賞することができました。それは自信に繋がり、プロとなった今も支えになっています。すでにオリジナル曲がある人や曲を作りたいという衝動に駆られている人もチャレンジしてみるといいんじゃないかな。

鈴木雄太郎:草田くんと同じ、第1回のSeikoSJC に参加しました。当時、大学4年生の僕はビッグバンド・サークルの仲間とセッションをした動画で応募したんです。つまり、オーディションに向けた練習は特にしていないんですよ。そんな僕が言えることは、自らハードルを上げずにフットワークを軽くしてチャレンジするのもいいんじゃないかってこと。ありのままの状態で応募すれば実力試しにもなりますからね。

山崎:雄太郎さんが言っていたように、僕もありのままの自分でオーディションを受けました。応募するしないに関わらず、日課として基礎練習はほぼ毎日やっていたので、それが良い結果につながったのかもしれません。飾った自分で受かったとしても楽しめないと思うので、無理せず、今の自分ができることを演奏して、それを提出すればいいんじゃないかな。
Q:音楽を生業にすると決断した時、どのような不安がありましたか?
山崎:僕は高校を卒業したら絶対にプロになろうと決めていました。そのためにもニューヨークの語学学校に通うつもりでいたんですが、コロナ禍になってしまい、いきなり不安しかない世の中に変わってしまったんです。上京したのは20歳の時です。まだまだコロナ禍真っ只中でライブハウスは営業していない、果たして音楽の仕事はあるのか、家賃や駐車場代は払えるのか、といった不安だらけ。でも、最悪、お金が無くなったら実家のある名古屋に帰ればいいやと思っていたのも事実です(笑)。おかげさまで、今、プロのドラマーとして生活できているのは、やはり、人との出会いが大きいですね。コロナ禍の時に仕事が休みになってしまったプロミュージシャンとセッション会場で知り合い、その方たちと今もご縁が続いていますし、SeikoSJCで出会った仲間と共に、今日、リーダーライブをすることもできました。ライブに来てくださっているお客さまとの出会いも含めて本当にありがたいと思っています。
鈴木雄太郎:大学を卒業した後、僕は就職し、5年間ほど楽器店で働きました。3年経ったらミュージシャンになろうと思っていたのですが、丁度その時にコロナ禍に入ってしまったのでそのまま会社員生活を続けていたんです。でも、いつ、コロナが終息するかわからないし、30歳になるまでにトライしなければ絶対に後悔すると思い、27歳の時に会社を辞め、音楽活動に専念することにしました。もちろん、不安しかなかったですよ。決まった額の給料をもらう生活から一転、1日いくら、月に何本演奏しないと生計はたてられない、といったことをシビアに考えましたから。お金の面では確かに不安定ですが、それでも今、ミュージシャンの道に進んだことを後悔していません。不安を払拭する心の支えがあるからです。それはSeikoSJCで信頼関係を築けた同世代の仲間たちです。

廣橋:僕も音楽を仕事にする不安はありました。でも、仮に違う道を選んだとしてもやっぱり、不安はつきものだと思うんです。同じ不安を抱えるのであれば、自分が納得できる不安の方がいいかなと。SeikoSJCに参加したこともプロの道に進む後押しになりました。音楽を志す人たちとつながり、一緒に演奏することができて、しかも、それを生業としている講師の方々や通訳をしてくださっている方々(注:SeikoSJCでは通訳は英語のできる音楽講師が担当)、運営している人たちといった音楽に携わっている関係者の存在を知ったことで、僕はこういう人たちと今後も関わりを持ち続けて行きたい、いや、自分ならできるという可能性を感じたんです。
草田:僕の場合、ミュージシャン以外の選択肢を想像できなかったので、意気込んでプロになったわけではないんです。だから、特に不安を感じたりはしていなかったというか、あくまで人生の喜びとして音楽を続けているんですよ。もちろん、こうして音楽が仕事になり、自分が書いた曲を様々な人と共有できるのは本当に嬉しいことです。ただ、この先、ミュージシャン生活を続けられなくなるような出来事が起こるかもしれません。その時に自分と向き合うための鏡として音楽を捉えられるかというのがキャリアを積み重ねていくために大事なのかもしれない、と最近感じています。